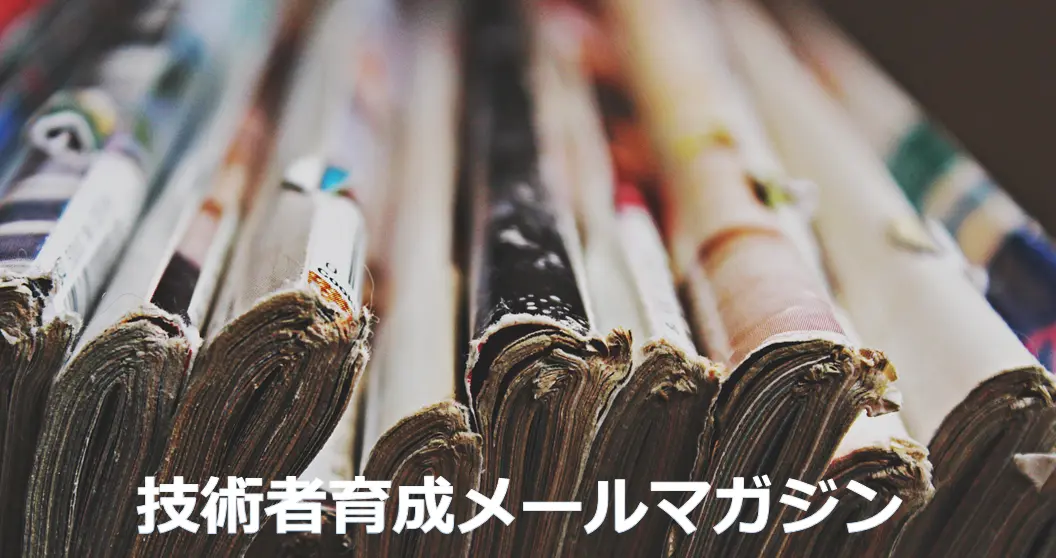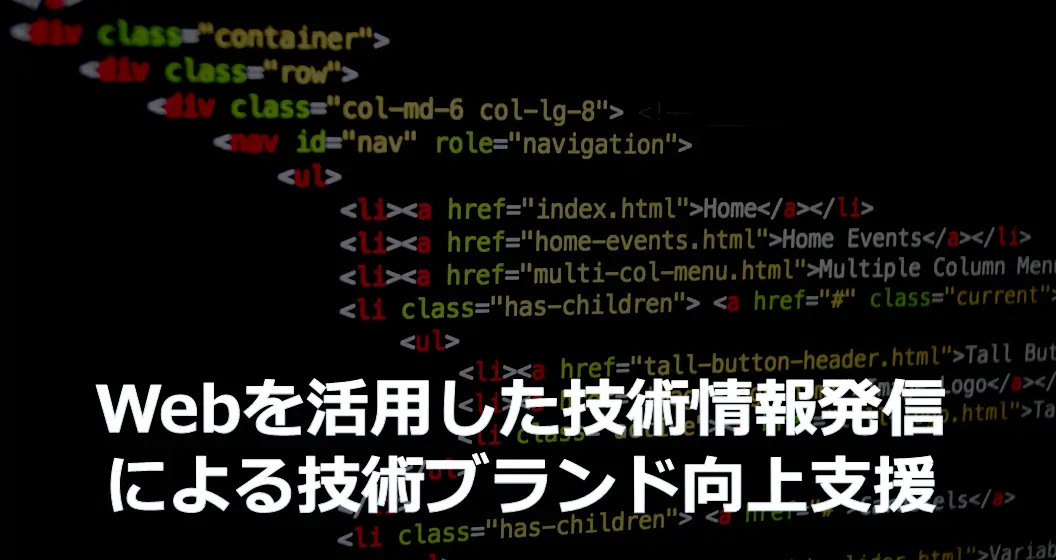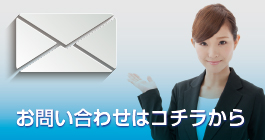何故、技術報告書作成が必要なのか
公開日: 2024年12月30日 | 最終更新日: 2024年12月29日
タグ: OJTの注意点, メールマガジンバックナンバー, 技術報告書, 技術者の普遍的スキル, 技術者人材育成
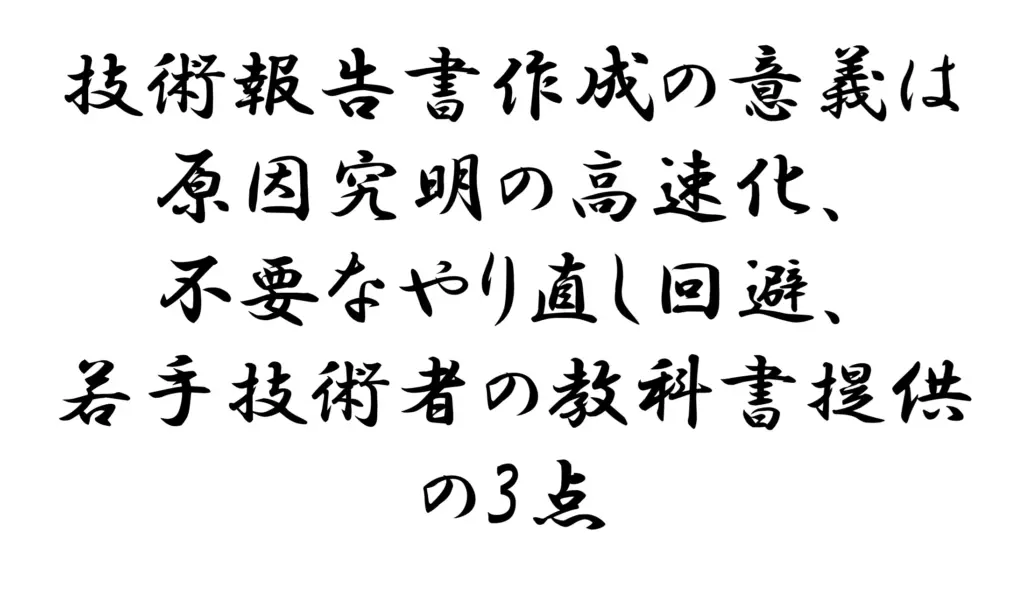
若手技術者が実験や試験の推進はできるものの、
技術の伝承として最重要媒体の一つである技術報告書の作成ができない状態にあるとします。
この状態を変えて、技術報告書作成を定常的な技術業務にしたいと、
リーダーや管理職が考えたとします。
これにむけリーダーや管理職がまず推し進めるべきは、
「そもそもなぜ技術報告書の作成が必要なのか」
ということの現場への理解浸透です。
そこで今回は、若手技術者に伝えたい技術報告書作成の意義について考えます。
技術報告書は技術者育成だけでなく技術伝承の要
技術報告書は若手技術者が、
業界不問の普遍的スキルを身につけるための最適の鍛錬手法であることに加え、
技術報告書そのものが技術伝承の役割を果たせるなど、
その波及効果は大きいものがあります。
※関連コラム
| 技術的知見をまとめるには目次が最重要 |
| 技術伝承の難しさ |
| 技術伝承を可能にする実験/試験動画の技術報告書への応用法 |
このような背景を踏まえると、
若手技術者のうちから技術報告書を書けるようにさせることは、
企業の技術力の基礎づくりに不可避とも言えます。
実験や試験は”やった感”が出るため地味な技術報告書作成より優先順位が高くなる
製造業企業に属する技術者が、実験や試験を推進することは当然ながら重要な業務です。
実際に試験や実験を行わないと得られない事実や結果があり、
それが次に何をするかの判断材料になることを考えれば当然です。
ここで改めて考えたいのが、何故技術者の多くは技術報告書作成を後回しにする、
もしくは避けようとするのかについてです。
現場で手足を動かしていると周りから見て頑張っていると見えやすいがPCの前に座る技術者の貢献度は見えにくい
これは事実である面もあります。
席に座ってPCばかり見ている技術者を事務所で見れば、
いったいこの人は何をやっているのだろう、となるでしょう。
このような話は、
「彼(彼女)はいつも席に座っているが、それでいいのですか」
といった形で遅かれ早かれ、その技術者の上司に到達します。
監督責任もある上司にあたるリーダーや管理職は、
「事務所でPC作業をすることも大切だが、現場の設備を動かすことも同じくらい重要だぞ」
といった趣旨の言葉を技術者にかけることになります。
言われた技術者は、
「では技術報告書作成などの業務を後回しにして、現場に行こう」
となります。
技術報告書作成を重要業務として定義している企業を除き、
上記のやり取りの繰り返しによって技術報告書作成業務というものが先細りしていきます。
技術報告書作成業務が好きな技術者はかなりの”少数派”
加えて前述の流れを助長するのが、技術者自身の考えです。
これまで業界問わず多くの技術者の指導を行ってきましたが、概ね共通しているのが
「技術報告書作成は好きではない」
ということです。
好きではないことをリーダーや管理職が、
意図しない形でも技術報告書作成業務の優先順位を落としていいと発言することは、
技術者にとって願ったりかなったりのはずです。
このように若手技術者だけでなく、中堅技術者、そしてリーダーや管理職のほぼ全員が、
技術報告書作成業務は”後でもいい”と考えている以上、
当該業務遂行の確率が低下することは避けられません。
しかし技術者育成を通じて企業の技術チームを強くしたい場合、
何かしらの手を打つ必要があり、その一つが技術報告書作成の意義に関する理解の浸透です。
技術報告書作成の意義を考えるには技術報告書作成が滞る企業での課題理解が有効
ここから本題である技術報告書作成の意義について考えます。
この意義を理解するには技術報告書という技術情報伝承媒体が無い、
もしくは不足する企業で生じる問題例を知ることが重要です。
以下、問題例を示します。
市場問題や品質問題など、大きな問題が生じた際に原因究明する”よりどころ”が無い
一番大きいのはここでしょう。
特に研究開発段階での技術報告書が不足していると、
開発段階を経て量産後に発生した各種問題に直面した時、
「生じた問題の解決につながる技術情報が不足する」
事態に必ず直面します。
例えば品質問題で生じた現象が、
研究開発の段階で類似したものとして確認されていたとします。
技術報告書があればどのような条件でそれが発生し、
また考察でどのような原因があるのかに関する記述があれば
生じた現象に関する関連情報入手が可能になります。
逆に、研究開発段階や量産立ち上げ段階で技術報告書作成の手間を省くと、
後に大きな問題としてのしかかることになります。
10年前に行った実験や試験をもう一度行い、同じミスを繰り返す
これもよくある話ですが、実験や試験を行ったがうまく結果が得られない問題が生じたとします。
その原因を究明しようと方々に話を聞くと、
「10年前に前任者が全く同じ問題に直面し、それを評価方法の変更によって解決していたことがわかった」
という事例です。
過去に起こった問題に関する情報が不足していたため、二の轍を踏んでしまうのです。
前任者が社内に居れば、上記のような話を聞くで何とかなるかもしれません。
定年等で既に前任者が居なければ過去知見を知る術がないのです。
技術報告書という記録の不足が、
後進に”無駄な”業務をやらせることに直結します。
効率が重視される昨今において、是が非でも避けたいことではないでしょうか。
細かいことを若手技術者に教えることに時間を取られる中堅技術者
若手技術者に実験や試験を適切に行わせるにあたり、
時に細かいノウハウや注意点を中堅技術者が伝えなくてはいけないことがあるでしょう。
それくらい自分で考えてやれ、
という職人的な技術者育成をすべて否定はできませんが、結局若手技術者は
「どうしたらいいのかわからず手が止まる」
だけです。
若手技術者の担う各種技術業務が遅れ、
その結果、中堅技術者はそのフォローを行うことで自らの業務が遅れるという、
”遅れの連鎖”が生じるでしょう。
ここに技術報告書が存在すれば、
実験項に手順を細かく記載するのが鉄則ですので、例えば
「この技術評価の手順は今説明した通りだ。
細かい注意点含め、技術報告書の〇項に記載してあるので、わからなければ質問してほしい。」
という指示の出し方で、若手技術者の技術業務推進確度を高めることが可能になります。
若手技術者は技術報告書を手元において技術業務の確認作業ができるからです。
このように、技術報告書は様々な技術業務のノウハウ伝授としての教科書の役割も果たせるのです。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
技術報告書指導において重要なのは、
当社のように外部から作成指導する側も、
ある程度技術を理解しなければならない点です。
これは技術者の多くが有する専門性至上主義により、
指導する側が技術者の方々の技術的な部分に関心を示し、
かつ分からない場合はそれを習得しようという姿勢を示さなくては、
当該技術者たちが助言や提言をはじめとした指導を受け入れないことが念頭にあります。
一般的な人材育成では技術業務とはあまり関係のない題材を用いることも多く、
また技術的な内容まで踏み込んで添削するといったことに対応しません。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
当社の技術者育成コンサルティングでの対応となります。
まず導入として技術報告書作成に関する研修を実施します。
この研修では課題も出し、
その添削を通じて技術報告書作成に関する理解の第一歩を踏み出していただくのが目的です。
その後、中長期での支援をご要望の場合、
技術報告書の基本構成を維持しながら、
各社が希望される技術報告書のテンプレートを作成します。
その後、当該テンプレートを用い、
現場の技術者の方々の抱える実業務を題材に技術報告書を作成いただき、
確認者である技術者(主に中堅技術者と管理職)と一緒に確認、添削作業を行い、
どのような観点で添削すべきかを指導します。
確認後は確認者から直接技術報告書作成者にフィードバックを行い、
作成者と確認者がともに技術報告書作成業務スキルを高められる流れを構築します。
上記の流れを何度も繰り返すことで、
技術業務に関して技術報告書を作成して文書化する、
という文化を醸成させることが可能となります。
まとめ
技術報告書作成の意義は、技術者が困難に直面した際に初めて痛感できることです。
言い方によっては結局最後は当人が大変な思いをしなければ、
本当の意味で意義を理解することはできないのかもしれません。
しかし、日々の技術業務推進の中で今回事例として示したような困難に技術者が直面した際、
”以前聞いたことのあるあの事か”と認識できることには大きな意味があります。
技術報告書作成業務が後回しになりやすい今だからこそ、
その意義を事前に伝え、
技術者が今回ご紹介した内容の話を本当の意味で理解できるきっかけを与えることが、
リーダーや管理職に求められる姿勢です。
是非職場で実行いただきたい取り組みです。
※関連コラム
| 技術報告書を書くために集中できるまとまった時間がとれない |
| 技術報告書には時間軸や個人名の記載は不要 |
| 最初に確認すべき技術報告書でよくみられるミス |
| 第7回 技術報告書を構成する最重要4項目 日刊工業新聞「機械設計」連載 |
| 第8回 技術報告書の2ページ目以降を構成する「内容」 日刊工業新聞「機械設計」連載 |
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: