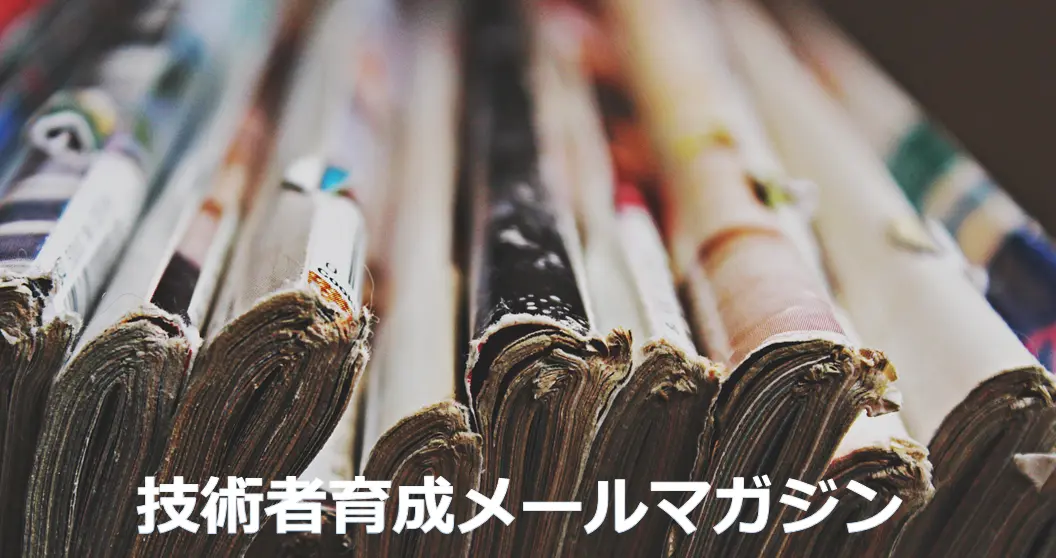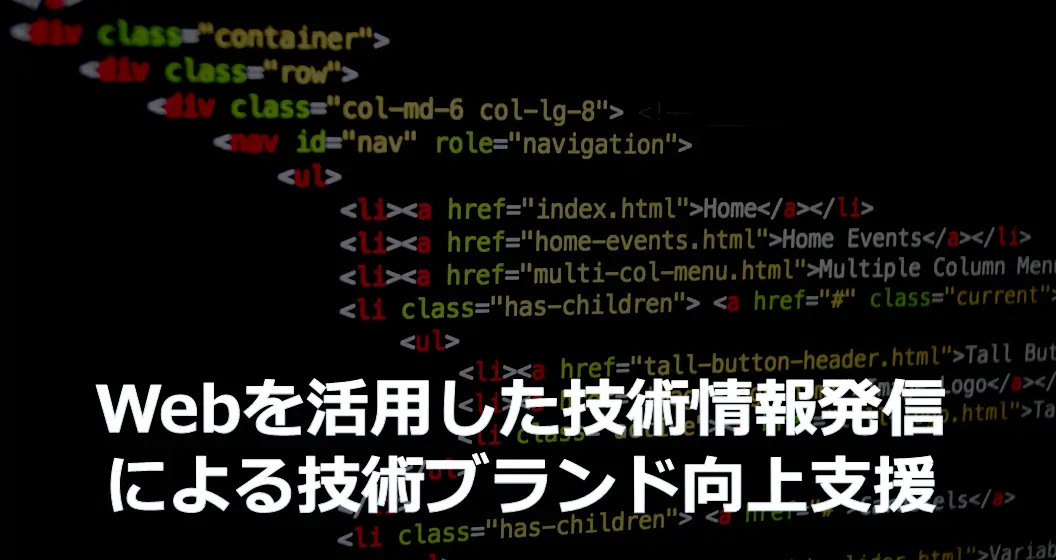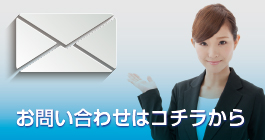若手技術者を活用して異業種技術を含む開発テーマの推進力を高めたい
公開日: 2025年3月24日 | 最終更新日: 2025年3月24日
タグ: OJTの注意点, イノベーションと企画力, メールマガジンバックナンバー, 技術者人材育成, 異業種協業
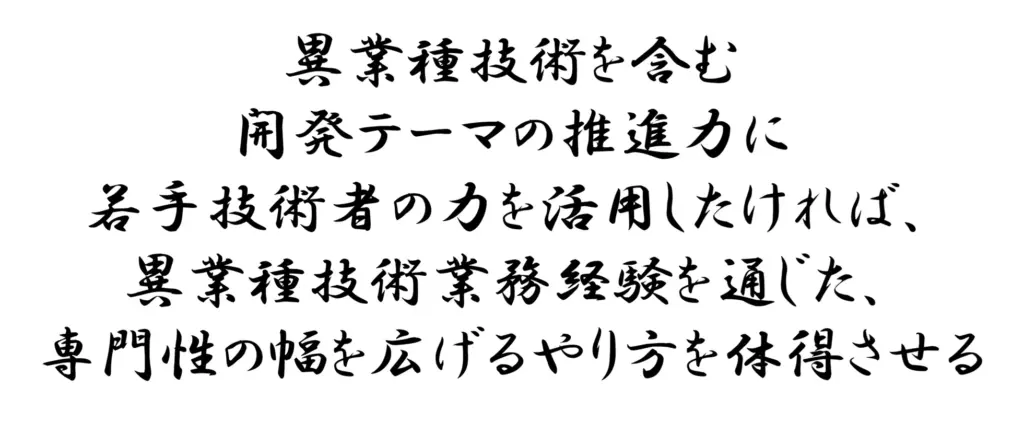
若手技術者を活用して開発テーマの推進力を高めるたい場合に、
リーダーや管理職に取り組んでいただきたい技術者育成の内容について考えます。
二極化が進む研究開発の流れ
製造業企業の研究開発の傾向として、
大きく2つの流れができていると感じます。
一つが自社技術の強みの徹底した深掘りと強化、
もう一つが自社技術を基軸にした他技術との融合化です。
自社技術の強みの徹底した深掘りと強化は日系企業が得意
長い時間をかけて高めてきた自社技術を更なる高みへもっていくことは、
日系企業が得意な傾向にあると感じます。
日本の義務教育を中心とした教育水準が平等で高いため自己学習のレベルが高く、
また終身雇用が主流のため一つのことを続けやすい環境など、
複数の要因があると考えますが、感覚的には上記の印象を持っています。
製造業の技術者というと、
ほぼ間違いなく町工場で加工設備を使う方々がメディアで取り上げられやすく、
また多くの方々のイメージもそのようなものだと思います。
こうして想起される技術者は”職人”としての色を示すことが多く、
何かを極めていくということについて、
日本では暗黙的に認知されているのかもしれません。
認められた職人のような技術者が集まれば、
そのような方々の属する企業の技術そのものになります。
技術者が日々その技術を高めるという取り組みが、
企業の技術力向上につながり、
個人依存性が高いゆえに簡単に真似されることがありません。
ただし、個人依存は技術の伝承や技術力向上に長時間必要など、
課題もあることは忘れてはいけません。
※関連コラム
自社技術を基軸にした他技術との融合化には異業種技術への歩み寄りが不可欠
研究開発のもう一つのトレンドが他技術との融合です。
流行りの技術に向けて猪突猛進するという意味ではありません。
あくまで、
「自社技術を軸にしながら、他の技術に”歩み寄る”」
のです。
この際に重要となるのが、
技術者の普遍的スキルの一つでもある
「研究開発に関わる技術者の”異業種技術への好奇心”」
です。
以下、この取り組みについてもう少し深掘りします。
異業種技術を有する相手から”教えてもらう”や”盗む”というスタンスだけでは技術の融合は不可能
異業種を有する企業と手を組んで研究開発を行い、
何か新しいものを生み出そうとする取り組みが、
”思ったほどうまくいかない”というのを見聞きしたことが多いかと思います。
その原因はケースバイケースですが、
技術者育成の観点から見ると以下のような要素が、
共通原因の一例となっているのではないかと考えられます。
偏った技術搾取正当性の崇拝
自らの技術の強みや課題を開示せず、相手から技術を盗もうとする。
上意下達が機能しないプロジェクトマネジメント不全
最初に声をかけた企業側が、何を求めているのかの要件を、現場レベルまで落とし込めていない。
研究開発に不適切な効率要求
予算や期限を厳しく設定し、腰を据えてお互いを理解するという猶予に乏しい。
第三者には無意味な仮面を取れない技術コミュニケーション
企業の規模やブランドといった、個々人の技術者のスキルと無関係な肩書に依存した態度で接する。
お互いに相手企業の技術を尊重し、理解しようとする”歩み寄り”が第一
技術者の普遍的スキルである”異業種技術への好奇心”の根底にあるのは、
「歩み寄り」
の精神です。
技術には”上下”はありません。
しかし技術的な分野が離れていればいるほど、
現場の技術者は相手の技術が分かりません。
そして技術者の中には自分が分からないことを認めたくない故に、
相手技術よりも自分の技術の方が上であると示すことに注力してしまい、
「どのようにすれば異なる技術を融合し、新たな技術が生まれるか」
という最重要の観点が失われることも多いのが実情です。
※関連コラム
ではこのようなことも念頭に、
若手技術者を活用して異業種技術を含む開発テーマの推進力を高めたい、
ということの実現に向け、若手技術者をどのように育成するかについて考えます。
異業種技術に関する業務に”触れさせる”ことからスタート
いきなり異業種技術を取り入れた研究開発に若手技術者をアサインするのは、
時期尚早です。
まずは小さな技術業務から始めてください。
この業務で重要なのは以下の点です。
- 自社技術と異なるが、将来的に自社技術との協業が”予想される”技術と関係がある
- 最長2、3カ月程度で完了する短期業務である
- 社内外で異なる技術専門性を有する人と基本的な議論が必要である
- 業務完了を判断する指標が明確である
上記のような観点を取り入れながら、
若手技術者に取り組ませる業務を振り分けてください。
若手技術者は異業種技術に対する許容力が高い傾向にある
今回取り上げたような異業種を含む研究開発に、
なぜ若手技術者を積極的に関わらせるかというと、
「若手技術者は実務経験が浅い故に、異業種技術を柔軟に取り入れられる許容力が高い」
という”強み”を有しています。
もちろん、専門性至上主義により自らが学校で学んだことにこだわりを有する若手技術者もいますが、
彼ら、彼女らは”若さ”という圧倒的なアドバンテージを有しています。
分からない、知らないからこそ、
様々なことに対して先入観無く取り組むことができるのです。
異業種技術を含む研究開発の糧となるのは当該業務の試行錯誤を通じた実践経験
若手技術者を異業種技術を含む研究開発で活躍させるには、
「異業種技術に関連した実務経験をさせる」
ことを通じた実践経験の蓄積を主とした育成が最も有効です。
そしてここでポイントがあります。
異業種技術が必要な理由、最終的なアウトプット、自己調査のやり方の明文化
リーダーや管理職は、
丸腰で異業種技術の業務を若手技術者に取り組ませないよう注意が必要です。
既述の通り先入観が無いことは強みである一方、
実務経験が浅いという弱みでもあります。
そのため、何の予備情報もないまま異業種技術の業務の中に放り込まれても、
若手技術者はどうしたらいいかわからず途方に暮れるでしょう。
この状態を避けるため、3つの柱となる情報を明文化し、
若手技術者に伝えることが重要です。
それが、以下の3点です。
- 異業種技術が必要な理由
- 最終的なアウトプット
- 自己調査のやり方
これらについて概要を述べます。
異業種技術が必要な理由
何故、その異業種技術が必要なのかを丁寧に誘導する意味合いがあります。
一番の理由は、
「あえて異なる技術に関する業務に取り組む動機づけ」
にあります。
自社の技術を活かすためには○○の技術が不足しており、
それを××という技術で補填することで、
既存技術に無い強みと付加価値を出すことができる。
そのような文言を、より詳細に、かつ丁寧に伝えられれば問題ありません。
口頭だけでなく、後から振り返られるよう明文化してください。
最終的なアウトプット
異業種技術に関する業務に取り組んでもらった結果として、
どのような形のアウトプットが欲しいかを示します。
こちらも具体的なものほど良いと思います。
例えば化学メーカの企業で機械加工で部品を作製したい場合を考えます。
化学メーカの方から見ると機械加工は未知の世界であることが多いので、
どのようなものを業務として求めるかを示す必要があります。
この例だと、以下のような内容になります。
以下の情報が揃ったものを、業務完了時に提出すること。
- – 形状と2D寸法と公差、並びに幾何公差が明記された図面に該当するpower pointのスライド
- – 対応可能な企業名称(複数あれば、すべて)とそれぞれの企業での見積もりと納期
- – 部品製作までの大まかなスケジュール
このように最終的に必要なものを明文化されることで、
若手技術者は自分たちが何を求められているのか、
理解することができます。
自己調査のやり方
異業種技術に関する業務で避けられないのが、
「自己調査」
です。
能動的活動によって、必要な技術情報を補填することです。
調査という単語を聴くと技術者の多くは、
「論文、技術雑誌、インターネットなどの情報を調べる」
と考えるかもしれません。
しかし上記の調査は一例でしかなく、例えば
- 技術業界の専門家(大学教員等)
- 業界の商流に詳しい人(商社やメーカの営業担当等)
- 社内の経験ある技術者
といった方々に”話を聞く”のも立派な調査です。
特に社内の技術者からの情報収集は盲点になりがちです。
それ以外にも、国会図書館を使うといった手法もあるでしょう。
このような調査方法について、若手技術者は必ずしも知っているとは限りません。
よって、リーダーや管理職は予め自己調査のやり方をいくつか示し、
必要に応じて活用する選択肢を若手技術者が理解することで、
技術業務の実践経験を通じた成長で最も重要な”試行錯誤”ができるようになってくるのです。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
異業種技術の観点を一般的な人材育成で例えるならば、
”異職種”の業務を学ぶといったイメージになると考えます。
例えば人事採用、経理、知財、営業、企画など、
総合職では様々な職種があります。
これらの職種では共通するスキルもある一方、
職種依存の知識もあります。
恐らく対応としては人材育成というよりは、
”業務の引き継ぎ”を通じて、
この辺りのスキルや知識の最低限の教育を行っていくのが一例です。
一方で技術者育成の観点では今回ご紹介したような、
異業種技術を応用した研究開発での活躍を見据えた、
自社技術には無い技術に関連する実務経験を若手技術者に積ませることを通じ、
将来、当該業務を能動的に進められるようになることを目指します。
そのため若手技術者に心構えを伝えることはもちろん、
リーダーや管理職が若手技術者育成に活用する異業種に関する技術業務の選定方法に加え、
若手技術者が能動的に進められるため、
どのような情報を準備すべきかについて指導することが含まれます。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
本支援の大前提は、
「実際に異業種技術を導入した研究開発がその企業で必要になっている(必要になることが間違いない状態にある)」
という意思統一が、社内でできていることにあります。
将来的に必要になるであろう、
という動機だけでは今回ご紹介したような技術者育成は困難になります。
何故ならば、知らない技術領域での取り組みを行うのは、
現場の技術者に多大なる負荷がかかり、
またリーダーや管理職もその管理が負担になることが多いためです。
動機づけが弱いと、育成指導を受ける側が受け身になるのです。
したがって
「若手技術者に異業種技術の実務を経験させる
という点だけを切り取ったような技術者育成コンサルティングは困難であることを、
予めご了承いただければと思います。
意思統一ができている場合、
- ・どのような異業種技術が必要なのか、その理由は何か
- ・現状の取り組みはどのようなことを行っているか、課題は何か
- ・育成対象の若手技術者だけでなく、技術チームの編成などリソースはどのような状況か
- ・いつまでに異業種技術を含めた研究開発をはじめ、そして完結させたいか
といったことをヒアリングします。
そのうえで、取り組みの計画について協議をしながら立案します。
特に若手技術者にどのような業務を割り当て、
それをリーダーや管理職がどう支援するかについて、
基本的なことをお伝えします。
そして計画に基づき、若手技術者に異業種技術に関する実務経験を積んでいただき、
その結果を踏まえながら必要なフォローを直接的、
もしくはリーダーや管理職を介して行うことで、
効率的なOJTを実現します。
まとめ
異業種技術を組み合わせた研究開発は、
これからますます重要になっていきます。
未知の世界へ飛び込むには、
若手技術者の有する若さは武器となります。
経験が無く、知らないことで、
不要なブレーキを踏まないのです。
ただリーダーや管理職がその若さに甘んじて丸投げしてはいけません。
異業種技術を融合した研究開発が近い将来控えており、
それに向けて異業種技術の経験を積んでほしいこと、
当該実務で求められるアウトプット、
さらにはもし困った場合、どのような調査を行うことが望ましいか、
といった点を活字として若手技術者に提供するといった、
支援が不可欠です。
今後ますます競争の激しくなる製造業の技術競争に勝ち抜くことを念頭に置いた、
若手技術者の取り組みとして参考になれば幸いです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: