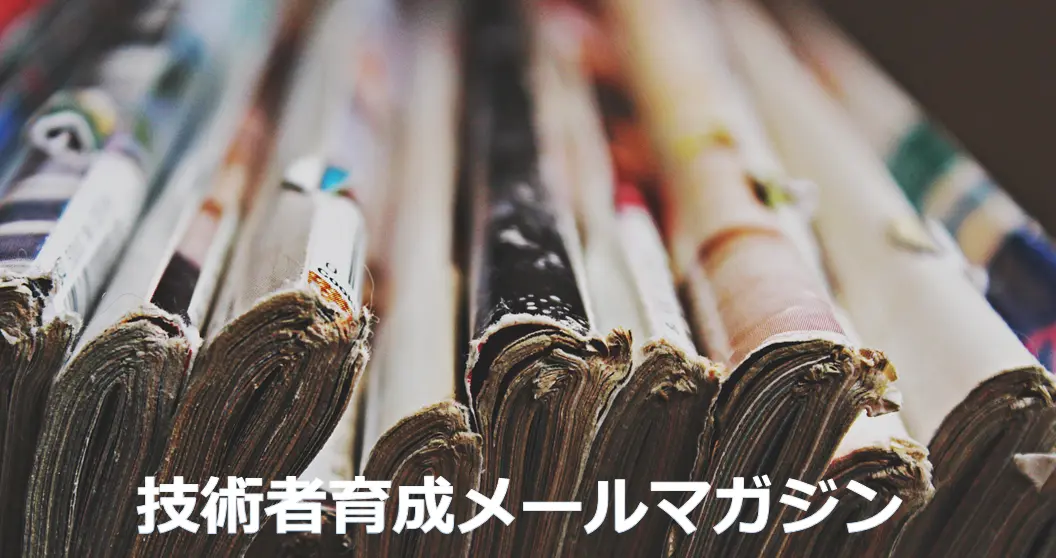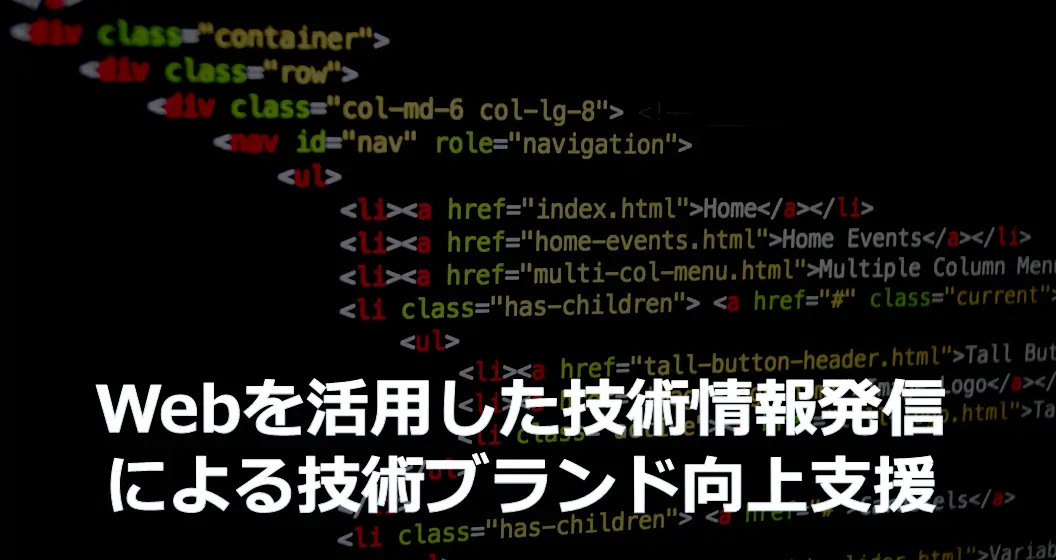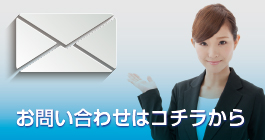優秀な中堅技術者が若手技術者に仕事を振り分けず抱え込んでしまう
公開日: 2025年4月21日 | 最終更新日: 2025年4月20日
タグ: OJTの注意点, できる技術者をさらに伸ばす, ジョブ型業務, 技術者のモチベーション, 技術者人材育成, 業務を抱え込む
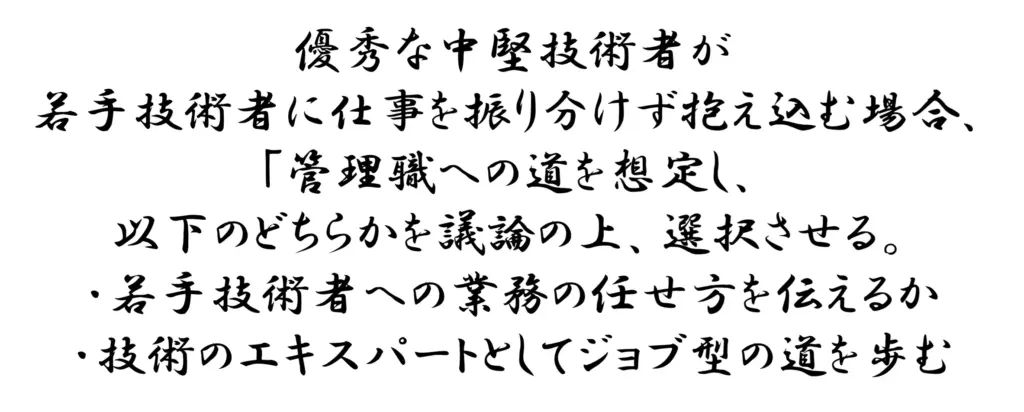
今回は若手技術者の育成に大変重要な技術業務の実践経験蓄積を中堅技術者が抱え込むことで妨害してしまう、という課題について考えます。
技術者育成効率化の鍵は当事者意識と”実践経験”
技術者育成は個々人の特性の影響を強く受けることもあり、
万能というものは無く、十人十色という表現の方が正しいです。
この前提において本質を突き詰めていくと、
ほぼ全員の若手技術者の育成に必要なものとして2つのことに行きつきます。
それが当事者意識と実践経験です。
やらされている感や受け身では絶対に成長しない
どれだけ企業側が若手技術者を育成によって成長させたいと思っても、
当の本人たちに成長に対する熱意や危機感が無ければ成長しないのは、
これまで多くの技術者を見てきて強く感じていることの一つです。
この成長に対する動機づけを高めるのも技術者育成の重要な一部ではありますが、
ここにリーダーや管理職が相応の熱量を注がなければいけないということは、
その時点で若手技術者が受け身である可能性が高いともいえるのです。
そのような中でも当事者意識を高めるにおいて、
効果的なものの一つが主担当、納期、明確な到達点という、
3点が揃った技術業務を完遂させることです。
研究開発の場合に効果のある本手法は、
それ以外の技術業務を担当する技術者に対しても当事者意識を植え付けるのに効果があります。
※関連コラム
将来研究開発を担う若手技術者の育成には中長期の研究は適さない
これ以外にも若手技術者の当事者意識に関することは、
過去に何度か取り上げたことがあります。
※関連コラム/連載
第19回 自分の仕事ではないと逃げる若手技術者への対応 日刊工業新聞「機械設計」連載
技術業務の実践経験は技術者育成の絶対的主柱
専門性至上主義を有する技術者が、
知識量を増やすことで存在感を高めたい気持ちはよくわかりますが、
結局のところ本質的な技術者の知見、すなわち”知恵”を獲得し、
技術者として成長するには実践経験しかありません。
研究開発に限らず、技術者としての仕事の多くは想定外のことが起こるのが普通で、
それを厳しい時間軸の中でやりきるしかありません。
ここで若手技術者が行わなくてはいけないのが”試行錯誤”。
試行錯誤は技術業務の中で同じ局面になっても、
技術者によって応答や感じ方が異なるため、
個人差が大変大きくなります。
この個々人の試行錯誤と、もがき苦しむ自分と向き合うことこそが、
専門性至上主義を抱える技術者に不足しがちな、
実践経験そのものになります。
本点も過去のコラムで触れたことがあります。
※関連コラム
以上の通り若手技術者の育成においては、
当該技術者自身の当事者意識に加え、
技術業務の実践経験が大変重要です。
若手技術者が技術業務の実践経験を積むにあたり中堅技術者が阻害要因になることも
リーダーや管理職が若手技術者の育成において、
当事者意識と技術業務の実践経験が重要と理解することは、
多くの企業においてそれほど難しいことではありません。
企業の中でそのような役職(リーダーや管理職)に抜擢される方の多くは、
若手技術者の成長こそが組織の維持発展に不可欠であることを、
大なり小なり理解していることが基本にあるためと考えます。
ここで意外にも立ちはだかる障害があります。
それが、
「中堅技術者(または、ベテラン技術者)の存在」
です。
むしろ若手技術者の育成において中心的役割を果たすべき彼ら、彼女らが、
何故障害となるのでしょうか。
そこにはいくつかの原因があるようです。
自分のやり方以外は絶対に許せない完璧主義
中堅技術者が優秀で、当事者意識が高い場合に起こるパターンです。
技術業務推進において技術的理論をきちんと理解し、
調査で終わらせずに試行錯誤しながら前進する実行力を有しており、
企業の中では技術業務推進能力は高いと評価されることが多いです。
そのような技術者は技術者の普遍的スキルが全体的に高く、
特に論理的思考力と技術文章作成力に優れます。
中には技術文章作成力には難があるパターンもありますが、
技術業務推進力という観点で力量があるのであれば、
ある程度の猶予を与えて成果を伴う成長を促すという考え方も有ります。
この辺りは過去にも取り上げたことがあります。
※関連コラム
いずれにしてもこのようなタイプの中堅技術者は、
「他の技術者に”任せる”」
ということが苦手な場合が多いのです。
若手技術者の試行錯誤や立ち止まりを許せない
仮にリーダーや管理職の指示により、
若手技術者に中堅技術者の抱える業務の一部を任せるようにしたとします。
不慣れな若手技術者は経験が不足している故、
思ったように結果が出ない、
ミスをするといったこともあるでしょう。
分からないことを調べ続け、
全く進まない可能性もあります。
冷静に考えれば若手技術者がそのような状態に陥るのは致し方ないのですが、
”自分ができること”を”できないこと”が理解できず、
「若手技術者に任せるより自分でやりたい」
と思うでしょう。
指摘が叱責のようになり、若手技術者が委縮する
特に遅延やミスが続くと、中堅技術者は修正や指摘をする際に”叱責”のニュアンスが強くなってしまいます。
- ・なぜ前と同じことを言わせるのだ
- ・なぜ教えたことができないのだ
- ・なぜそれほど時間がかかるのだ
- ・なぜそんなことも気が付かないのだ
自分を基準にして、上記のような”なぜ”を感じた中堅技術者は、
若手技術者の試行錯誤を見ていらない、
と感じるのでしょう。
任せようという気持ちがなくなるうえ、
指摘の一つひとつが妥当である故、
若手技術者にも重い一言となるでしょう。
このような状態が続くと、若手技術者は委縮してしまうに違いありません。
中堅技術者、若手技術者どちらが悪いというよりは、
お互いに歩み寄れない部分がどうしても生じる故、
それが障害となってしまうのです。
若手技術者への業務配分に対する中堅技術者の障害を低減するために
前述の状況は簡単には打破できませんが、
管理職はそれを放置するわけにはいきません。
技術系チームの生命線は人材の新陳代謝であり、
若手が常に入ってこない場合、
必ず地盤沈下を起こすからです。
やはり若手技術者の育成を重要視しなければならないでしょう。
ここで管理職は中堅技術者(場合によっては、ベテラン技術者)に対し、
一つの決断をしなくてはいけないと思います。
優秀な中堅技術者を管理職として
これは多くの企業において一般的なアプローチです。
中堅技術者も年齢を重ねるにつれ、
最前線で技術業務を担い続けることは言うほど簡単ではなくなります。
優秀な中堅技術者に対しては技術者としてだけでなく、
リーダーや管理職としての役割を担い、
組織をまとめる側に回ってほしいというのが、
企業側の本音だと思います。
中堅技術者には技術業務の実務以外の管理職に近い業務を与える
この場合、管理職が行うべきは、
「技術実務以外の業務を中堅技術者に与える」
ことでしょう。
予算編成や採用、研究開発テーマ企画などがその一例です。
こうすることで徐々に技術業務に割ける時間が減ることを実感させます。
同時に、技術業務の実務部分を若手技術者に振り分けるよう、
管理職は中堅技術者に指示を出してください。
結果として、中堅技術者がいつまでも実務を抱える状況ではなくなり、
若手技術者に技術業務を振り分けざるを得なくなるのです。
優秀な中堅技術者を技術を極めるエキスパートとして
近年、当社への問い合わせでも増えてきているアプローチです。
管理職側ではなく優秀な中堅技術者やベテラン技術者には技術を極め、
それをもって組織に貢献するという道を歩ませると言い換えて問題ありません。
採用の観点でもこのようなスキルプランが用意されていることは、
技術職への就職を希望する学生にとって魅力的に映るでしょう。
技術者としての実務経験のある私個人としても、
その流れは尊重すべきと考えます。
一方で忘れられがちなのがその具体的手法と、
技術のエキスパートとして生きることの厳しさです。
業務はジョブ型が基本
具体的な手法というのは、ジョブ型の技術業務を設計・提案し、
中堅技術者と議論の上、技術業務に邁進させることです。
エキスパートという職種は、その取り組むべき業務内容や、
求められる成果が極めて明確でなければなりません。
ジョブ型の技術者は、雇われているという感覚をある程度捨てなければなりません。
管理職側は従来の何となく指示を出す、場合によっては放置するといったことは許されず、
与えた業務に対し、求めた成果を出したか否かを客観的に評価する、
俯瞰的視点が求められます。
よって評価しやすいように業務設計をする必要があり、
管理職にとっては大変な労力となるに違いありません。
さらには職務として求められたこと”以外”は、
”やらなくてもいい”という働き方を、
管理職だけでなく、職場の全員が理解し、受け入れ、
その働き方を尊重することも不可欠です。
異分子のような扱いをしているようでは、
優秀な中堅技術者がジョブ型として働く環境には遠く及ばないでしょう。
ジョブ型については過去にも何度か取り上げたことがあります。
※関連コラム
ジョブ型の働き方を選んだ中堅技術者は安定を求めてはいけない
無意味な会議や管理業務から解放され、与えられた技術業務を通じて、
要求された成果を求めて自己研鑽しながら技術業務に注力する。
これは技術者の新しい働き方の一選択肢といえるでしょう。
そして給与面でもエキスパートである以上、
一般的な正社員よりも高額にし、
自己裁量に任されるため出社頻度に対する要求もないなど、
労働条件変更も十分にあり得ます。
ここまで聞くといいことばかりのように感じるかもしれませんが、
当然ながら正社員と比べて厳しくなるものもあります。
・技術のエキスパートには無期限雇用は望めない
一番は、
「有期期限雇用」
でしょう。
エキスパートで生きていこうという覚悟を決めた以上、
技術者であっても安定雇用の前提を要求してはいけません。
短ければ数カ月、長くても一年ごとの契約更新のイメージになります。
成果ですべてが認められている以上、致し方ないことです。
逆に言うとエキスパートの道を歩もうとする中堅技術者は、
業務に対する成果物を明確化する時点で、
企業側ときちんと条件をすり合わせることが求められます。
業務契約とかはわからないので、法務にやってもらいたい、
という考えもエキスパートの世界では甘えです。
必要に応じて自分で弁護士を探して相談する、
といった対応が必要となるでしょう。
・リスクヘッジは必須
求められた技術業務をきちんと完遂したものの、
成果が得られなかったということも当然あるでしょう。
それを致し方ないと企業側が判断すれば良いですが、
予算状況や社内外の情勢によって異なる判断が出ることもあるでしょう。
突然、中堅技術者の働く場所がなくなる可能性もあるのです。
そのような状況に備え、本当に自らの技術に自信があるのであれば、
今勤務している企業”以外”で技術業務を並行して推進できるよう、
リスクヘッジをするという姿勢が必要です。
・ジョブ型は若手技術者と協業する必要はない
もしジョブ型を中堅技術者が選んだ場合、
前述の厳しい条件と引き換えに、
若手技術者に仕事を振り分けるといったことを考える必要はありません。
それはリーダーや管理職の仕事になります。
結果的に若手技術者に業務を振り分けないという中堅技術者由来の障害は、
取り除かれることになります。
中堅技術者の技術業務を少しずつ若手技術者に移していく
ここまで述べてきたような選択肢を中堅技術者に示して選ばせることで、
管理職は中堅技術者の抱える技術業務を少しずつ若手技術者に移していく、
という取り組みが必要となるでしょう。
管理職系の道を歩めば技術業務に関わりにくくなり、
ジョブ型を選べば雇用安定性を失うという選択肢は、
どちらも中堅技術者にとっては一長一短です。
ただそこから逃げるのではなく、
中堅技術者はこのようなことになる可能性も念頭に、
若いうちから目の前の技術業務に精一杯取り組み、
自己研鑽をするという意識を持ち続けることが必要で、
それが企業にとっても望ましい姿です。
そして若手技術者も年齢を重ねていつか同じ道を歩む可能性がある以上、
中堅技術者は気持ちよく若手技術者に成長の機会を与えるべきでしょう。
このような心地よい緊張感も、
これからの技術者育成にも大切なのではないでしょうか。
優秀な中堅技術者が若手技術者に仕事を振り分けず抱え込んでしまう状況を打破し、
若手技術者に技術業務の実践経験を積ませる取り組みのご参考になれば幸いです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: