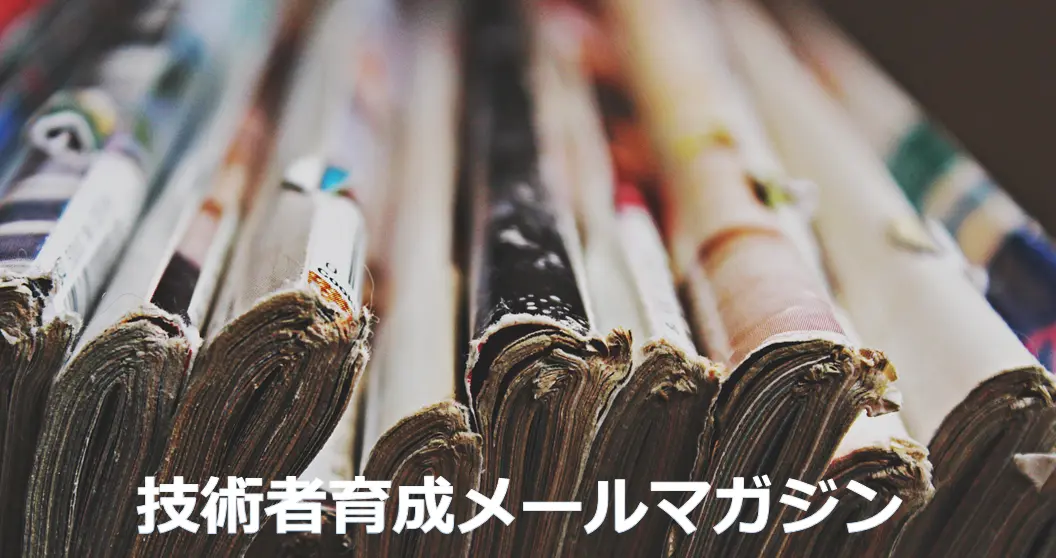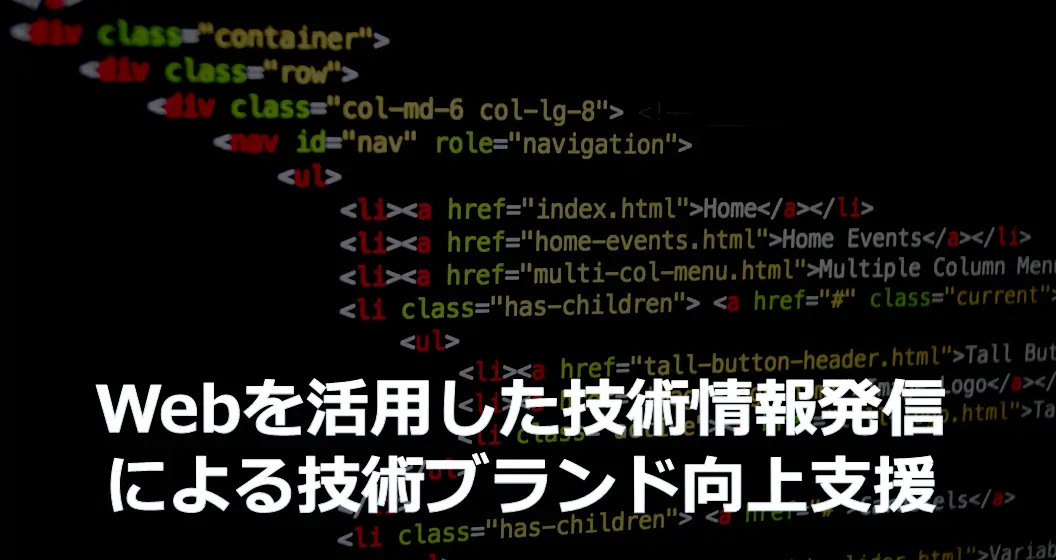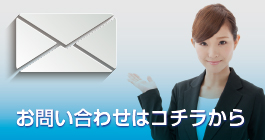課題解決型の業務経験を期待する新人技術者の受け入れ研修内容の最重要点
公開日: 2025年4月7日 | 最終更新日: 2025年4月21日
タグ: メールマガジンバックナンバー, 技術報告書, 技術者のモチベーション, 技術者の上司とは, 技術者の癖, 技術者人材育成, 課題解決
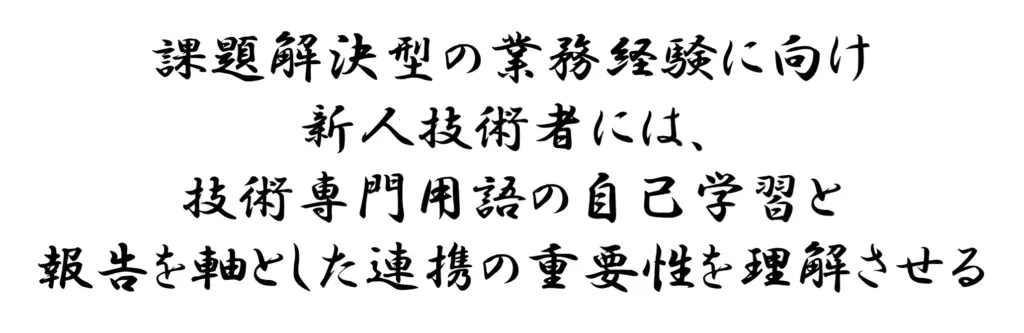
今回は主に新入社員である技術者(以下、新人技術者)が期待する”課題解決型の業務経験”に向け、
新人研修等で取り入れたい大変重要な2つの準備について述べたいと思います。
課題解決型の業務経験は新人技術者が期待するものの一つ
先日、非常勤講師として10年目を迎えた福井大学での理系学生(主に学部3年、4年)向けの講義において、
「企業のインターンなどで経験してみたいことは何か」
と投げかけたところ、
「課題解決型の業務経験」
という回答が複数得られました。
インターンが当たり前になりつつある昨今、
何となくの業務経験ではなく、
ある程度の目的意識を持って企業と接したい学生の意思を感じています。
この意識は実際に入社した後も大きくは変わらないと考えられ、
新人技術者のリアリティーショックを緩和する意味でも、
企業側は課題解決型の業務経験ということを念頭に、
新人研修等を設計することが求められます。
※関連コラム
研究開発系の若手技術者のリアリティー・ショックを緩和するには
探求型意識を高めるという教育方針も影響か
2025年4月1日の毎日新聞電子版で、以下のような記事が出ました。
高校教科書検定 探究型意識、随所に工夫 授業の転換、道半ば(毎日新聞電子版:2025年4月1日)
この”探求型意識”という単語が、前述の課題解決型の業務経験への期待の一因となっている可能性を感じています。
探求型意識を持つことは新人技術者にとても重要
最初に断らなければならないのは、
教育方針である探求型意識は新人技術者にとても重要である、
という事実です。
研究開発であれば新しい技術の発展や創出には、
技術データの少しの変化や小さな結果を見逃さず、
それがなぜ起こったのかをきちんと見極める探求心が必要です。
品質保証であれば市場問題などが起こった場合、
起こった事象の原因を”客観的”に見極めるため、
製造時のプロセスデータを丁寧に見直し、
問題発生ロット製造時に変曲点が存在しないか等を丁寧に調査したうえで、
問題の起こった製品を様々な分析技術を用いて明らかにすることが求められます。
こちらも探求心が基本となっています。
探求心を育てる一つの方向性は、新人技術者(若手技術者)に知的好奇心を持たせることです。
この辺りは過去のコラムでも述べたことがあります。
※関連コラム
思考型教育は暗記型教育を土台にしないと成立しない
探求心を育てるには思考型教育が重要である、
という趣旨の記事やメディア上での発言は多く見られます。
そして対となる主張として、
教育において暗記は悪であるというものがあります。
なぜ、関係の深い思考型と暗記型が対になってしまうのかは個人的にはよくわかりませんが、
上記のような論調を見聞きした方は多いものと考えます。
ただ実際はそれほど単純ではありません。
結局のところ思考型教育も知識が前提となっており、
ある程度の暗記は避けられないからです。
例えば技術系の思考型科目の代表例である数学も、
暗記の側面が多くあります。
思考を求められる整数問題を例にしても、
最も基本である偶数や奇数を自然数nを用いてどう表記するか、
そもそも整数と自然数、無理数と有理数といった単語の意味を理解できていなければ、
整数問題で議論を展開することは不可能です。
暗記量が比較的少ない物理も同じです。
こちらも例えば放射性物質のある一定期間後の残留物質を、
半減期を使ってどのように算出するかは、
一度数学的な証明を行うにしてもその流れを理解し、
結果として暗記しなければならないでしょう。
運動方程式や等速円運動などの公式も、
その算出方法含めて理解の結果、覚えることが求められます。
化学、生物、地学等の理科系科目もその多くは暗記が土台です。
※関連コラム
暗記しなければならない知識を”部品”として扱えるようになって、
初めて思考型の取り組みができます。
部品を持たない技術者が思考型の言動、
特に新人技術者が期待するような課題解決型の実践で活躍するのはほぼ不可能でしょう。
よって、知識習得に向けた暗記は悪であるという決めつけは危険であることを、
新人技術者はもちろん、受け入れる側のリーダーや管理職、
教育担当の社員の方々の共通認識とすることが不可欠です。
※関連コラム
課題解決型業務をできたという実感で承認欲求を満たしたい新人技術者
教育的側面に加え、新人技術者側の心理も理解することがリーダーや管理職に求められます。
新人技術者の多くは、深層心理として専門性至上主義を有していることは、
過去に何度も述べています。
※関連コラム
しかし入社後は自分の無力さに直面する場面もあり、
自信を失う出来事が多いでしょう。
「自分は専門的な教育を受けてきたのに何故通用しないのか。」
といった自己嫌悪にも近い心理になることもあるのではないでしょうか。
ここで新人技術者の中で高まるのが承認欲求です。
-
- 自分は企業で戦力になっているという実感が欲しい
- 知識ではなく”考えたこと”で結果を出したと感じたい
- 自分が課題解決に関わるというチャンスをもらったことを他者に認めてもらいたい
このような承認欲求の高まりも、冒頭で紹介した”課題解決型の業務経験”への欲求の高まりを後押しするでしょう。
以上の通り、教育的、そして心理的背景もあって新人技術者の多くは”課題解決型の業務”を早い段階で経験したい、と考える傾向にあります。
新人技術者の気持ちや学校教育に関する潮流は理解できるが、技術者育成の観点から見ると誤解や間違いが多い
ここまでご紹介した新人技術者の気持ちや、
学校教育に関する潮流は個人的に理解できるものばかりです。
否定するつもりもありません。
しかしながら研究開発の現場での実務と、
様々な企業の技術者育成に携わってきた自らの立場から言えば、
「産業界で活躍する技術者には課題解決型の早期実務経験よりも、
”技術的な知識を能動的に学習する姿勢”と”報告を主とした周りとの連携”を強く求めたい」
のが本音です。
このような考え方こそが結果的に、
「課題解決型の業務経験」
だけでなく、その業務経験を通じた、
「自己成長と企業組織への貢献」
に直結します。
上記を実現するために新人技術者に理解、そして実行させたいことについて2点述べます。
技術的な専門知識習得は自己学習が基本
1点目は教育という観点では否定されることもある暗記です。
技術者育成で最も重要な”技術者間の議論”をつかさどる基本構成要素は、
”技術専門用語”に他なりません。
よって技術業務で良く用いる技術専門用語を、
理解の上で”暗記”するのは大前提です。
このような技術専門用語は”教えてもらうもの”だと考える新人技術者や人材育成関係の方もいるようですが、そのような受け身の姿勢では技術専門用語の習得効率は上がりません。
企業は教育機関である学校ではないのです。
よって新人技術者の方々が大学や大学院、専門学校などで学んだ
「自己学習」
を実行することが求められます。
必要な知識は自分に合うやり方で、自分なりに学ぶという意識が技術者には大変重要です。
一度覚えたものを忘れてもいいのです。
試験で高得点を取るのが目的ではなく、
「技術的な議論の内容を理解し、その議論に参加することで自らが技術的に成長する」
ことが狙いだからです。
もし自己学習に対する理解が不足している新人技術者がいるようならば、
本点を補足するような研修を行うのが一案です。
※関連コラム
”報告”を基軸にした周りとの連携
報連相が重要という基本は新人技術者でも同じです。
すべてできるに越したことは有りませんが、
この中で強いて技術者が重視すべきは何か、
と問われればその答えは
「報告」
です。
”相談”は探求型意識を高める思考型教育の影響や、
大学や大学院の研究室生活での自己完結の考え方が染みついているため、
新人技術者だけでなく、若手技術者、人によっては中堅やベテラン技術者でもできない方が多い。
また、”連絡”も多くがメールやチャットで簡単に済ませることで、
自らの思考時間を捻出したいという意識が前出の技術者では優先的に出ることが多く、
こちらも簡単に教育等で修正することはできず、時間をかけて指導する必要があります。
しかし”報告”だけは、仮にそれが苦手であってもできなければなりません。
報告があれば技術業務状況などをリーダーや管理職が把握でき、
必要に応じた指示や指導を行うことも可能だからです。
”報告”をきっかけに周りの社員と連携することを覚えさせる
そして最も大きいのが報告をきっかけとした、
「周りの社員との連携」
です。
新人技術者も含め多くの若手技術者がそうであると考えますが、
「技術業務を自分の力で完結させたい」
という意識を持っていることが多いです。
これ自体は当事者意識という意味では妥当ですが、
技術業務推進の大前提である”連携”という概念が欠落しています。
技術者一人で進められるような技術業務は、
そのスケールに限りがあります。
特に新人技術者が望むような課題解決型の業務経験につながるような実務では、
社内外の様々な組織や方々との連携が不可欠です。
報連相の”連”と”相”は難しくとも、
報告だけは死守するという意識で、
日々の技術業務に取り組む経験を新人技術者に積ませてください。
これがチームプレーの理解への第一歩であり、
課題解決を実行できるような技術者への道の始まりといえます。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
新入社員に対して課題解決型の業務経験をさせることは、
一般的な人材育成でも重視される傾向にあります。
自社の課題を抽出し、その課題を明確化したうえで、
課題解決に向けた計画の立案とその推進を支援する、
といったアプローチが一例です。
これに対して技術者育成では、
大前提として技術専門用語の習得と、
”報告”を最重要視した技術業務推進方法の指導を行います。
技術専門用語の習得は能動的に行うという基本を徹底指導します。
技術業界は多岐にわたりますが、
各業界の技術専門用語の複数を例に挙げ、
それらの意味だけでなく、技術的な応用方法や活用法についても、
リーダーや管理職を通じて指導するよう促します。
報告の方法としては、技術報告書の作成法指導に始まり、
技術チームミーティングの運営方法と議事録作成法、
ミーティングにおける技術的議論の深め方についても提案を行います。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
技術専門用語の自己学習への促しについては、
最初に各企業がどのような教育体制を有しているかをヒアリングの後、
改善、変更の必要がある場合に限り、各種提案を行います。
自己学習は個々人の性格に依存したやり方が主となるため、
必要に応じて新人技術者や若手技術者に個別面談を実施し、
各人に指導を行います。
技術業務における報告の徹底については、
技術報告書を軸に、技術チームミーティングの準備、推進、記録の残し方について、
書面を中心としたやり方の提案を行います。
必要に応じて実際に社内の打ち合わせに同席して状況を理解した後、
リーダーや管理職に対して各業務推進の提案や指導を行います。
まとめ
新人技術者は企業の成長の糧となる大変貴重な戦力です。
学校教育方針の変化により課題解決への執着が強い新人技術者が増加傾向にあることを踏まえ、
企業としては早い段階で当該関連業務を経験させるという戦略が重要です。
この戦略の着実な実行前の準備教育として、
技術専門用語の自己学習と技術業務における報告の徹底は不可欠であり、
本2点を徹底的に理解させるという企業側の姿勢が肝要となります。
課題解決型の業務経験を渇望する新人技術者に向けた、
技術者育成のご参考になれば幸いです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: